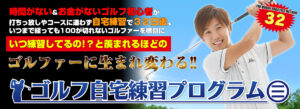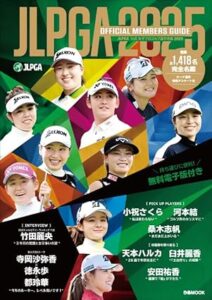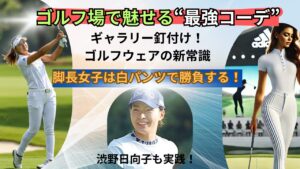おいおい、またか?
「ウェッジは3本がいいですか?4本がいいですか?」 って、そんなの聞く前に、プロのプレーをちゃんと観てるのかい? 🤨
渋野日向子プロだって、2022年頃までは ウェッジ4本体制 だったんだぜ?
それが今じゃ、50°・54°・58°の3本体制にシフトチェンジ。
「何でだろう?🤔」って思ったお前さん、センスあるじゃねぇか!
クラブ本数を変える=プレースタイルの進化 ってことを、うっすら感じ取ってるってわけだな。
でもな、ここで終わるんじゃねぇ。
本当に「プロの選択の意図」を理解したいなら、 クラブスペック記事を眺めてニヤニヤしてるだけじゃダメだ!
🔍 答えは“プロのリアルなプレー”にある。
グリーン周りでの「ピッチ&ラン」
バンカーショットでの「フェース開き具合」
ウェッジ選びの判断基準や“打つ直前の微調整”――
そういう「生きた技術」は、VODでプロの動きを“盗み見”するしかないんだよ!
この記事では、
- 渋野プロが ウェッジ4本→3本に変えた理由
- プロによって違う ウェッジ選びの戦略
- そして、VOD観戦でショートゲームを学ぶ極意
…この辺を、俺がしっかり教えてやる!😎
最後まで読んだら、きっとこうつぶやくはずさ。
「VODでプロのウェッジショット、じっくり観たくなってきた…」 ってな!
🎯 **さぁ、行くぜ!ウェッジ選びの“真実”を暴いてやろうじゃねぇか!**🔥

🧠 なぜウェッジの本数選びは重要なのか?

「100ヤード以内を制する者がゴルフを制する」――
これは、ゴルフ界で昔から言われてる“真理”だな。🏌️♂️🔥
ドライバーでかっ飛ばしても、アプローチで寄せられなきゃ “ナイスボギー” で終わり。
逆に、100ヤード以内をビシッと寄せられれば、パーやバーディのチャンスが倍増するってもんよ!
で、その100ヤード以内を制する鍵が、そう――
ウェッジの本数選び ってわけさ。
⚖️ ウェッジの本数がスコアに影響する理由
「ウェッジなんて2~3本あれば十分でしょ?」って思ってるお前さん、ちょっと待ちな。
実は、ウェッジの本数次第でスコアメイクの“しやすさ”が全然違うんだぜ。
なぜかって?
それは、アプローチで求められる3つの要素が変わってくるからだ。👇
🎯 アプローチで重要な3つの要素
- 距離感:
ウェッジのロフト差が小さいほど、振り幅を一定にするだけで距離感が掴みやすい。 - 弾道の高さ:
ウェッジの本数が増えれば、低めのピッチ&ランから高めのロブショットまで対応力がUP。 - スピンコントロール:
ロフト角が変わることで、スピン量の調整幅が広がり、攻めのバリエーションが増える。
🟢 ワンポイント!「ウェッジの本数が違うと何が変わる?」
| 🚩 本 数 | 🎯 メリット | ⚠️ デメリット |
|---|---|---|
| 4本体制 | 距離感を「振り幅」で調整でき、弾道の選択肢が豊富。 | クラブ選びに迷いやすく、ロングゲーム用クラブが1本減る。 |
| 3本体制 | クラブ選びがシンプルで、プレッシャー下でも迷いが少ない。 | 距離感を「感覚」で掴む必要があり、ミスが増える可能性あり。 |
社長、それって要するに ロフト角の違い=打ち出し角とスピンの違い って話ですよね?



おぉ、うんちく王子。言いたいことはわかるがな…
お前さん、“数値”で語る前に、プロのウェッジショットの高さやバックスピンを “目で観て” 理解したことあんのか?
えっ?…い、いや、まだですけど、理論的には…



理論だけじゃダメなんだよ!
渋野日向子プロが ピッチ&ランで転がすか、ロブで上げるか…その選択の瞬間を、VODでじっくり観察してこそ “使える知識”になるんだ!



え~?でも、テレビ中継でもプロのショットって見れますよね?



ちあきちゃん、それが“大きな勘違い”だ!
テレビ中継じゃ、ショットの瞬間だけが映ることが多い。
でも VOD観戦なら、ショット前の“クラブ選び”や“ルーティン”まで全部チェックできるんだぜ!



えっ、それって… プロがウェッジを選ぶ“理由”がわかるってことですか?



その通りだ!
渋野プロが、なぜ 54°ウェッジをバンカーで使うのか?
なぜ 50°ウェッジでピッチ&ランを選ぶのか?――
その 思考のプロセスが、VOD観戦なら“見て学べる”んだよ!
🔍 渋野日向子がウェッジを4本から3本に変えた理由
さて、肝心の話に戻ろう。
かつて、渋野プロは 46°・50°・54°・58°の4本体制 だった。
でも今は、50°・54°・58°の3本体制 に変更。
この変化には、明確な理由があるんだ。


1️⃣ 飛距離アップに伴う“ギャップ調整”
渋野プロは飛距離が伸びてきて、ピッチングウェッジで 135ヤード超え を記録するようになった。
これに伴い、ウェッジ間の距離ギャップが変わり、 「50°・54°・58°」でバランスが良くなったんだ。
(注:135ヤード超えはあくまでも憶測です。)
2️⃣ ロングゲーム強化のための“クラブ再配置”
ウェッジを4本から3本に減らしたってことは、そのぶん “他の1本” を追加できるってことだ。
渋野プロの場合、ロングゲーム強化のためにユーティリティを追加した可能性が高い。
3️⃣ 攻めるゴルフへのシフトチェンジ
プロのショートゲームってのは、守りじゃなく攻めが基本。
渋野プロは 3本体制にしてアプローチ選択をシンプルにすることで、
迷いなくピンを狙う姿勢を強化したってわけだ。



プロのクラブ選びってのは、ただ“飛ぶから”とか“スピンがかかるから”じゃねぇ。
渋野プロのウェッジ選びをじっくり観察すれば、きっとその“理由”がわかるさ。
…で? どうやって観るかって? VODしかねぇだろ!
▶️ 渋野日向子プロの2025年最新クラブセッティングはこちら!


🟢 プロのウェッジ選びを“VOD観戦”で学ぶべき理由
「ウェッジ選びの基準なんて、プロの真似をすればいいでしょ?」
…そんな風に思ってるなら、それこそ “浅い” ってもんだ。
同じ4本体制でも、上田桃子プロはロブショット重視、
小祝さくらプロは転がし重視――プレースタイルによって選び方が全然違うんだ。
🎯 プロのウェッジ選びは“ライブで観る”だけじゃ不十分!
テレビ中継じゃ、アプローチショットの前後がカットされることが多い。
でも、VOD観戦なら、こんなポイントが “見える化” できる。
🔍 VOD観戦でわかる3つの“プロの選択の裏側”
- ショット前のクラブ選びの迷いゼロな姿勢
- 構えた瞬間のフェース開閉のわずかな動き
- 打った後、どのくらいランを計算してるかの“反応”
🎙️【VOD観戦で得られるヒント】



でも、VOD観戦で何を観ればいいかわからないかも…💦
いや、それは簡単さ。
①アドレスでクラブフェースがどう向いてるか
②打つ前にどこを見ているか
③打った後、ボールの落とし場所を確認しているか――
この3つを観察すれば、アプローチの勘がわかるって理論があるんだ!



わぁ!うんちく王子、ちょっとカッコいい…かも…💦
そ、そりゃ、まぁ…VODでちゃんと研究してるからね!



ま、まぐれ当たりにしちゃ、なかなかイイ線いってるな。
でもな、その“3つの観察ポイント”、
実際に VODでプロのプレーをじっくり何度も観たからこそ、得られた知識だってこと、忘れんなよ!
🎯 ウェッジ選びの答えは、VOD観戦にあり!
ウェッジ3本 or 4本――
その選択がゴルフのスコアに大きく影響すること、もう理解できたか?
渋野プロのセッティング変更も、プレースタイルの進化を支えるための決断だったんだ。
そして、こうした「選択の意図」を知るためには、プロのプレーを“生で観る”ことが一番。
📺 \今こそ、VODで女子プロのウェッジ選びを学ぼう!/
- 「ピンを狙う渋野日向子プロのアプローチ」
- 「転がしを多用する小祝さくらプロのクラブ選び」
- 「ロブショット名人・上田桃子プロのフェース使い」
…これらを VODでじっくり観察 すれば、あなたのウェッジ使いも格段に進化するはずだ!



ウェッジは“数値”じゃなく、“目で盗む”もんだ!
さぁ、お前さんも VOD観戦でプロの秘密を盗みに行ってこい!
📲 \今すぐ“プロのウェッジ戦略”をVODで観てみよう!/
👉 VOD観戦でプロの技を盗む!
🛠️ 渋野日向子がウェッジ3本体制に変更した3つの理由


ウェッジ4本体制から3本体制への変更――
これ、ただの「クラブの数合わせ」だと思ったら大間違いだ。
渋野日向子プロが 46°・50°・54°・58°の4本体制 から、
50°・54°・58°の3本体制 に切り替えたのは、明確な意図があってのこと。
さぁ、プロがウェッジ本数を調整する本当の理由を、一緒に覗いてみようじゃねぇか!🏌️♂️💥
🛠️ 距離ギャップの最適化
「ウェッジの距離ギャップ」――これが、渋野プロが3本体制に踏み切った 最大の理由だ。
飛距離が伸びたことにより、PW(ピッチングウェッジ)の飛距離が約135ヤードまで到達。
それに伴い、ウェッジ間の飛距離ギャップが広がりすぎちまったってワケだな。
🏌️♂️ 【Before:4本体制時の距離設定】
⛳️ クラブ 🎯 飛距離(目安)
PW(46°) 135ヤード
50°ウェッジ 110ヤード
54°ウェッジ 90ヤード
58°ウェッジ 70ヤード
このセッティング、当時の飛距離バランスを考えりゃ、悪くはなかった。
でもな、飛距離が伸びたことで、110ヤード付近の微妙なギャップが気になるようになったんだ。
🎯 【After:3本体制後の距離設定】
🏌️♀️ クラブ 🎯 飛距離(目安)
PW(46°) 135ヤード
50°ウェッジ 115ヤード
54°ウェッジ 95ヤード
58°ウェッジ 75ヤード
🔍 3本体制に変えた距離的メリット
PWと50°の飛距離ギャップが均等化
→ PWで135ヤード、50°で115ヤードという 絶妙な20ヤード差 が完成。
30~100ヤードの距離感がシンプルに!
→ 50°・54°・58°で 30・50・70ヤード付近の打ち分けがしやすくなった。
アプローチの“打ち分け判断”が楽になる
→ 「この距離ならコレ!」と即決できる。



飛距離が伸びると、ウェッジ選びも変わるんだよ。
渋野プロは “距離の迷い”をVODで確認してたに違いねぇ。
お前さんも プロの距離感合わせを、VOD観戦で盗んでみろ!
🚀 ロングゲーム強化のためのセッティング変更
ウェッジを1本減らすってことは、クラブ枠が1つ空くってことだ。
プロのセッティングってのは「14本全部ギリギリ」まで考え抜かれてる。
ウェッジを4本→3本にした背景には、ロングゲームの強化という狙いがあった。
🧠 ウェッジ1本減で増えた“攻撃力”
ユーティリティの追加で、200ヤード付近の攻略力UP!
ウッドの本数を増やし、コース戦略を多彩に!
飛距離ギャップが埋まり、パー5の2オンチャレンジが可能に!
海外ツアーじゃ、200ヤード前後のショット精度が問われる。
渋野プロはウェッジ1本減らして、ロングゲーム強化に全振りしたってわけだ!
社長!つまり、ウェッジ4本→3本にしたのは、ロングショット重視ってことですか?



おうよ!海外ツアーじゃ 200~220ヤードを正確に狙うクラブが重要だ。渋野プロはそこに目をつけて、ウェッジを1本減らして、ユーティリティを追加したんだな。
うわぁ…!確かに 米ツアーのコースって長いですもんね!
でも…そのぶん、アプローチは難しくなりません?



だからこそ、ウェッジ3本で打ち分ける技術をVODで研究してるんだよ。
…お前も “VODでプロのウェッジ術”、覗いてみな!
🔥 攻めの姿勢への変化
渋野プロってのは、元々 攻めのゴルフ が信条のプレーヤーだ。
でも、ウェッジが4本あると、どうしても選択肢が増えて、迷いが生まれる。
そこで、3本体制に切り替えて、“打ち方”と“狙い”をシンプルにする作戦に出たんだな。
🎯 攻めの姿勢を強化する3本体制のメリット
選択肢が少ないから迷わない!
→ ピンが近けりゃ54°、奥なら50°、上げるなら58°――これだけ覚えりゃOK。
攻撃的アプローチが可能に!
→ 迷わず打つことで、インパクトが安定し、ピンをデッドに狙える。
プレッシャー下でも冷静に判断!
→ クラブ選択で悩む時間が減ることで、メンタルの余裕が生まれる。



ウェッジ選びで悩む時間?
渋野プロはそんなもん、最初から作らねぇんだよ。
…その**“決断の速さ”**を知りたいなら、VODでスロー再生してみな!
🏆 ウェッジ3本体制の理由は“戦略的進化”にあり!
ウェッジ4本から3本へ――
この変更は、飛距離アップ・ロングゲーム強化・攻めの姿勢強化という、
渋野プロの戦略的進化を支える決断だったんだ。
🎯 ウェッジ3本体制の3つのポイント
📏 飛距離ギャップの最適化:飛距離向上に合わせてウェッジ間のギャップを整備。
🚀 ロングゲーム強化:ウェッジ1本を減らし、ユーティリティを追加。
🔥 攻めの姿勢強化:選択肢を減らして、迷いなくピンを狙うゴルフに転換。



プロがウェッジ本数を変えるのには、必ず理由がある。
渋野プロが攻める姿勢を“本気で強化”したその背景、
VODで実際のプレーを観りゃ、さらに納得できるはずだぜ!
📲 \今すぐ“プロのウェッジ戦略”をVODで観てみよう!/
👉 VOD観戦でプロの技を盗む!
⚖️ ウェッジ3本vs4本!アマチュアに最適な選び方とは?


お前さん、ウェッジの本数を「何となく」で決めてないか?🤨
「プロが3本だから、俺も3本でいいや」――そんな安易な考えで、アプローチが安定するわけがねぇ。
実は、ウェッジの3本体制と4本体制は、ただの本数の違いじゃない。
プレースタイルやコース戦略、
そして100ヤード以内の考え方そのものが変わってくるんだ!
さぁ、ここで 3本vs4本のガチンコ勝負 を見てみようじゃねぇか!🏌️♂️🔥
✅ ウェッジ4本体制のメリット
🎯 距離感をつかみやすい!
ウェッジ4本体制の最大のメリットは、距離感の“型”が作りやすいことだな。
ロフト角が細かく分かれてる分、
「スイングの振り幅=距離」って法則が体に染み込む。
たとえば、時計の針スイングを使えばこんな具合だ👇
- 50°ウェッジ:9時 → 80ヤード、10時 → 95ヤード、11時 → 110ヤード
- 54°ウェッジ:9時 → 65ヤード、10時 → 80ヤード、11時 → 95ヤード
こうやって 「振り幅を一定にするだけで距離感が身につく」のが、4本体制の強みだ。
🎯 ショットバリエーションが増える!
ロブ、ピッチ&ラン、バンカー、ランニングアプローチ――
ウェッジの本数が多ければ、そのぶん「引き出し」が増える。
- グリーン奥にピンが切られたとき → 50°で低く転がす。
- バンカー越えのショートサイド → 58°でハイロブを打つ。
この “クラブを選ぶ=アプローチの選択肢が増える”のが4本体制の醍醐味よ!



アプローチの“引き出し”を増やしたいなら、4本体制が手っ取り早い。
でもな、“使いこなせるかどうか”は、お前さん次第だぜ?
❌ウェッジ4本体制のデメリット
⚠️ ロングゲーム用クラブが1本減る!
ウェッジを4本入れるってことは、ロングゲーム用のクラブを1本削る必要がある。
例えば、4本体制のために 5番ウッドやユーティリティを抜いた結果、
200ヤードのパー3で「何を使えばいいんだ?」って大慌て…なんてことも。
⚠️ クラブ選びで迷いやすい!
ウェッジが4本あると、状況ごとに「どれを使うか」で迷いやすくなるんだな。
特に、こんな状況で頭が真っ白になるアマチュアは多い👇
- 残り70ヤード:50°?54°?58°?
- グリーン手前の花道:50°で転がす?54°でふわっと?
迷いすぎると、スイングのリズムも乱れて、結果は… ザックリ、トップ、そして涙目ってな。



社長~!ウェッジ4本って、何だか頭がこんがらがりそうですね💦



ははっ、ちあきちゃん、その通り!
4本体制ってのは、距離感練習にはもってこいだけど、実戦で即判断するのは難易度高めだ。



やっぱりプロってすごいんですね…
いや、それだけじゃない!プロたちは試合前に“距離感練習”を徹底してるんだ。
例えば渋野プロも、練習場で各ウェッジの飛距離と弾道を“VODで確認”して復習してるらしいですよ!



えっ、VODって“ただの観戦ツール”じゃないんですか?



甘いな、ちあきちゃん!
VOD観戦=“プロの練習メニュー”を盗み見る特権だってこと、覚えときな!
✅ ウェッジ3本体制のメリット
🎯 クラブ選択がシンプル!
3本体制最大のメリット、それは迷いのなさだ。
**50°・54°・58°の3本構成なら、「距離=振り幅」「状況=ロフト選択」**がシンプルになる。
例えば…
- ピッチ&ラン → 50°
- ピン位置中央 → 54°
- バンカー越えのロブ → 58°
迷わず打てるから、スイングに「キレ」が出るってわけだ!
🎯 ロングゲームを強化できる!
ウェッジを1本減らすってことは、
ユーティリティ・フェアウェイウッド・5番アイアンなど、ロングゲームクラブを1本追加できる。
特に、飛距離が必要な海外コースや、ロングホールでの2オン狙いには欠かせない選択肢になる。



ウェッジ3本で攻めるってことは、ロングゲームの選択肢を増やす“攻めの姿勢”でもあるんだよ!
❌ ウェッジ3本体制のデメリット
⚠️ 1. 距離感を“感覚”で合わせる必要がある!
ウェッジが3本だと、クラブで距離を埋めるのが難しくなるんだな。
例えば、残り70ヤードのとき…
- 54°の軽いスイングか?
- 50°のコントロールショットか?
この判断を感覚だけで決めなきゃならないのが、3本体制の難しさってわけだ。
⚠️ 練習量が必要!
プロは3本でも距離感をバッチリ合わせるけど、それは練習量の賜物だ。
スイングの振り幅や打点を安定させるため、プロたちはVODで自分のフォームを徹底分析してるんだ。
- プロの練習風景をVODで観る
- ウェッジショットのインパクト位置を観察
- フェースの開き具合&スイングスピードをチェック



お前さん、距離感を磨きたいなら、VODでプロのウェッジ練習を観察しな!
練習場で“何を意識してるか”が、きっとわかるはずだ!
🎯 結局、アマチュアには3本?4本?
さぁ、お前さんならどっちを選ぶ?
3本体制?それとも4本体制?
🟢 4本体制がオススメな人
- 距離感に自信がなく、振り幅で感覚をつかみたい人。
- ショートゲームを鍛えて、“アプローチマスター”になりたい人。
- クラブ選びをじっくり考え、状況に合わせてショットを使い分けるのが好きな人。
🔴 3本体制がオススメな人
- 攻めのゴルフが好きで、迷わずピンを狙いたい人。
- ロングゲームを強化したい、飛距離派ゴルファー。
- 練習熱心で、距離感を“感覚”でつかむ自信がある人。
社長、これって結局、プレースタイル次第ってことですよね?



おっ、たまには鋭いな!
守りのゴルフなら4本。攻めのゴルフなら3本。結局は自分のゴルフをどう魅せたいかって話だ。
なるほど…。
でも、渋野プロが実際に3本体制でどう攻めてるか、もっと知りたいんですよね…。



おぉ、その意気だ!
なら、VODで“渋野プロのウェッジテク”をじっくり研究してみろ。
クラブ選びの瞬間、打つ前のルーティン、そして打った後の反応――
全部、VOD観戦の中に答えが転がってるぜ!
🏆 ウェッジ選びのヒントはVODにある!
ウェッジの3本・4本体制――
この選択は、あなたのゴルフにとって重要なターニングポイントになるかもしれない。
そして、その答えを知るためには…
「プロが実際にどうプレーしているか」を自分の目で確かめることが何より重要だ。
🔍 \VOD観戦でプロのウェッジ使いを“盗み”に行こう!/
- 渋野日向子プロの50°ウェッジでのピッチ&ラン
- 古江彩佳プロの精密なバンカーショット
- 小祝さくらプロの絶妙な距離感アプローチ
これらをVODでじっくり観察すれば、
あなたのウェッジ使いも、次のレベルに進化するはずだ!



ウェッジ選びは奥が深ぇぞ!
記事を読むだけじゃなく、VODでプロのプレーを観察して、自分のアプローチ力を爆上げしてこい!
📲 \今すぐ“プロのウェッジ戦略”をVODで観てみよう!/
👉 VOD観戦でプロの技を盗む!
🧠 ショートゲーム戦略の秘密は「VOD観戦」にある!
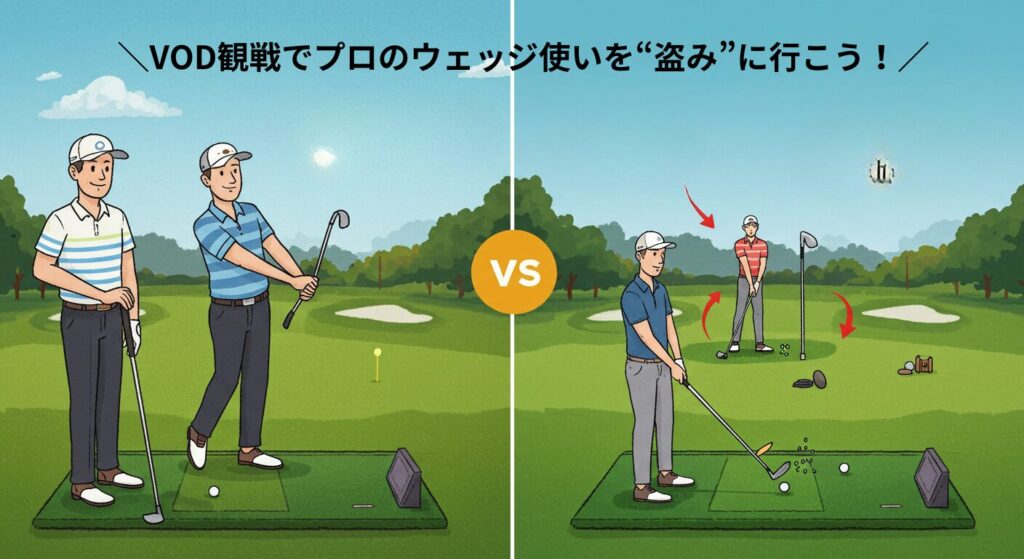
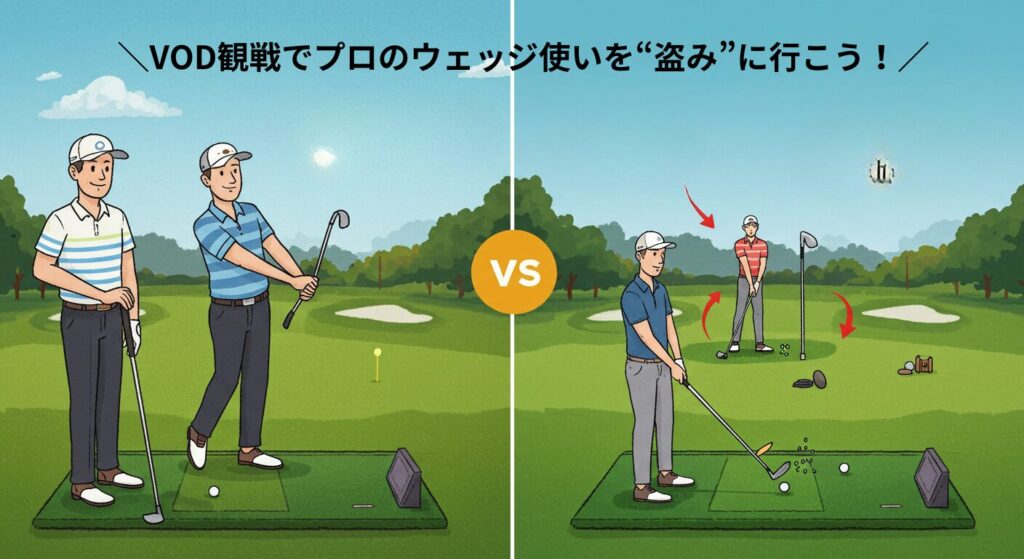
「ウェッジ選びなんて、ロフト角と飛距離がわかれば十分でしょ?」
…そう思ってるお前さん、それじゃ“机上のゴルフ”だ。
プロのショートゲームが“異次元レベル”って言われる理由、知ってるか?
それは、クラブ選びの判断基準・スイングの微調整・状況判断力――
こうした 「教科書には載っていない技術」を身につけてるからなんだよ!
でもな、その秘密をテキストや数値だけで理解するのは至難の業。
なぜなら、アプローチ技術は「観て学ぶ」のが一番早いからだ。
🎯 なぜ“VOD観戦”がショートゲーム上達に効くのか?
ゴルフ中継でプロのプレーを観たことがあるだろ?
でも、テレビ中継ってのは 「ショットの瞬間」しか映らないことが多い。
⛳️ たとえば、こんな“重要な場面”がスルーされてるんだ👇
- 🧐 クラブ選択の瞬間:プロが 何を考えてウェッジを選んでいるのか?
- 🔍 アドレス前の素振りや調整動作:どういう打ち方をイメージしてるのか?
- 🌬️ 風やライの確認プロセス:打つ前に何を確認しているのか?
📺 これらの“プロの思考の軌跡”――
テレビじゃ観られねぇが、VODならじっくり何度でも観察可能なんだよ!



社長、でも VOD観戦って、普通のゴルフ中継と何が違うんですか?🤔



いい質問だな、ちあきちゃん!
テレビは“結果”を見せるための放送だけど、VODは“過程”を観るためのツールなんだ。
あっ、わかります!
テレビ中継ではショットの瞬間ばかり映して、“どのクラブを選んで、どう構えたか”はわかりませんもんね!



おっ、珍しく話が早ぇな。
だからこそ、お前らもVODで“プロの思考プロセス”を観察するべきなんだよ!



なるほど!
じゃあ次のラウンド前に、渋野プロのウェッジショットをVODで見てみます!
🚀 VOD観戦で得られる3つの学びポイント
🟢 ウェッジ選択の理由がわかる!
ウェッジの使い分け、これがプロとアマチュアの最大の差だ。
同じ50ヤードのアプローチでも、
- 渋野日向子プロは 50°でピッチ&ランを選ぶのか?
- それとも 54°で軽いスピンをかけるのか?
その選択理由を理解するためには、打つ前のクラブ選びの瞬間を観る必要がある。
👀 VODで注目するポイント:ウェッジ選択のプロセス
- ボール後方でクラブを持ち替える場面:
→ 50°から58°に持ち替えた理由は何か? - グリーン周りでの打つ前の確認動作:
→ 左足体重?右足体重?ライをどう読んでるか? - キャディとの会話シーン:
→ **「風の読み」や「ピン位置の攻略計画」**が聞けることもある。



プロがクラブを決めるまでの“間”を観察しろ!
渋野プロのVODをスロー再生すりゃ、**“あ、この瞬間に攻めに決めたな”**ってのがわかるはずだ!
🔵 アプローチショットのテクニックが盗める!
プロのアプローチは、**打ち方の“引き出し”**が桁違いだ。
同じ30ヤードでも――
- ピッチ&ランで「コロコロ転がして寄せる」
- フェースを開いて「スピンをかけて止める」
- ロフトを立てて「低く速い球で転がす」
状況に応じて最適な技術を選ぶ能力がずば抜けてるんだよ!
🎯 VODで注目するポイント:プロのアプローチテク
- フェースの開閉具合:
→ ロブショットのとき、どれくらいフェースを開いてるか? - インパクト後のフォローの取り方:
→ ピッチ&ランなら低く短く、ロブなら高く長く。 - 打つ前の素振りのクセ:
→ 打つ前に何度か同じ素振りをしてる場面に注目!
社長!渋野プロのバンカーショットって、スイングスピードが速いですよね?



そうだ!バンカーはスピン量を砂でコントロールするから、スイングスピードが肝だ。
…で?その“速さ”をどうやって知ったんだ?
VODをスロー再生して、テークバックからインパクトまでの時間を計測しました!



ハッ!いいじゃねぇか、その調子だ!
プロの技術は“目で盗む”――お前もやっと、VOD観戦の楽しさに気づいたってわけだな!
🟠 プロの「決断の早さ」と「状況判断力」を体感!
プロのアプローチで一番すげぇのは、
「決断の速さ」と「迷いのなさ」だ。
アマチュアはアプローチで、
- 「50°か?54°か?…いや、58°で行くべきか?」
- 「ピッチ&ラン?ロブ?…どうしよう…」
と、頭の中で悩んでる間に、プロはクラブを決めて振ってるんだよ!
🎯 VODで注目するポイント:決断力の秘密
- キャディと話す時間:迷ってるのか、即決してるのか?
- クラブ選択後のルーティン:クラブを決めたら、もう他の選択肢を見ないか?
- 風・傾斜・芝の確認作業:グリーンを読む際、どの順で確認してるか?



プロの“迷わない決断力”――
その秘密は、普段からVODでライ読み&クラブ選びを研究してるからだ!
お前さんも、渋野プロがクラブを決めるまでの時間、VODで測ってみな!
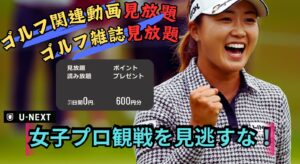
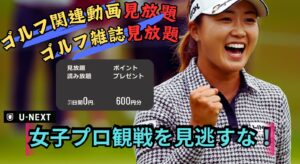
🧠 VOD観戦でプロのショートゲーム戦略を学ぶステップ
「プロのプレーを観る」――
ただそれだけじゃ、“ゴルフ観戦マニア”で終わっちまう。
“ゴルフ上達マニア”になるためには、こんな手順でVODを活用しろ!👇
🔍 ステップ1:ターゲット選手を決める
まずは、「この人みたいなアプローチをしたい!」と思う選手を選ぶんだ。






| 🏌️♀️ プロ選手 | 🎯 特徴 |
|---|---|
| 渋野日向子 | 攻めのピッチ&ラン、転がしアプローチの達人! |
| 古江彩佳 | 繊細なタッチでのロブ&バンカーショットが絶妙! |
| 小祝さくら | 安定感抜群!「無駄のないアプローチ」なら彼女から盗め! |
🛠️ ステップ2:ショットごとに“注目ポイント”を決める
VODを観るとき、ただ眺めて終わりじゃダメだ。
必ず「今日はアドレスの形をチェックする!」など、テーマを決めて観ろ!
🔍 VOD観戦テーマ例:
- アドレスの重心位置:左足?右足?
- フェースの開閉具合:開き具合とスイングの関係性
- 打った後のリアクション:プロが首を傾げるとき、何を感じてる?
📓 ステップ3:自分のプレーに取り入れてみる
VOD観戦後、練習場で必ず試すんだ。
「プロの真似をする」→「自分の感覚と比較する」→「再びVODで答え合わせ」
このサイクルを繰り返せば、アプローチの引き出しがグンと増えるぜ!
🏆 VOD観戦こそ、ショートゲーム上達の近道!
ウェッジ選びの知識だけじゃ、アプローチのレベルは上がらねぇ。
プロの技術、クラブ選び、スイングの工夫――
その全ては、VOD観戦で“目で盗む”ことで初めて理解できる。
- 🟢 渋野日向子プロの“転がし名人”アプローチ
- 🔵 古江彩佳プロの“ふわりロブショット”
- 🟠 小祝さくらプロの“手堅いアプローチ術”
これをVODで観察すれば、あなたのショートゲームも進化する!



プロのプレーをテレビで“観る”だけじゃ、アプローチは上達しねぇ。
でも、VODで“研究”すりゃ、お前さんのウェッジショットもプロ級になるかもしれねぇぜ!
🏆 VOD観戦で女子プロたちのウェッジ戦略を体感しよう!
「ウェッジ選びの正解は?」
その答えを、本やYouTube動画の解説だけで探してるお前さん、まだまだ甘いな。
ウェッジ選びの真髄は、“プロのリアルなプレー”を目で観て学ぶしかねぇんだ。
なぜって?
- クラブ選びのタイミング
- アドレスでの重心のかけ方
- ショット前後の微妙な仕草
こういう「生きた技術」は、数字じゃなく映像の中にこそ詰まってるからさ。
🎯 VOD観戦が「ショートゲーム理解」を深める理由
🎥 自由自在な“巻き戻し&スロー再生”で、プロの技を分析できる!
テレビ中継だと、ナイスアプローチが決まった瞬間、すぐ次の選手に切り替わっちまう。
でも、VODなら、あの名アプローチを何度でもスロー再生できるんだ。
たとえば…
- 渋野日向子プロが花道から50°ウェッジで転がしたシーン
- 小祝さくらプロがバンカーから高いロブで寄せた瞬間
これらを リプレイ&スロー再生することで、
- クラブ選びの根拠(なぜ50°を選んだのか?)
- フェースの開き具合(どこまで開いてる?)
- 打つ前の素振りの回数や軌道(なぜ2回素振りした?)
こうした“プロの考え方”を自分の目で確認できるんだ。
🛠️ 練習のヒントを“プレー映像”から盗める!
プロのショートゲームには、“ルーティンの習慣”が隠れてる。
たとえば、古江彩佳プロの“バンカー前ルーティン”👇
- クラブフェースを開いて砂の硬さを確認
- 足を埋めて、スイング幅を調整
- 打つ直前にボールの後ろをじっくり見つめる
こういう「無意識のルーティン」がプロの精度を支えてるんだ。


VODでこの“無意識の動き”を観察し、真似して取り入れる。
これが、ショートゲーム上達の最短ルートってワケだな。
🌪️ プロの“攻め方”をプレースタイルごとに学べる!
プロによって、同じ距離でも選ぶクラブが違うって知ってるか?
- 渋野日向子プロ:積極的に転がして攻める「ピッチ&ラン派」
- 西郷真央プロ:バックスピンでピタッと止める「スピンコントロール派」
- 小祝さくらプロ:確実に寄せる「リスク管理重視派」
この違いを知るだけで、アプローチ戦略の幅がグッと広がるんだよ。
VODなら、プロの狙い・使うクラブ・スイング軌道――
すべて“目で理解できる”ってワケだ!



社長、VOD観戦ってそんなに役立つんですか?💦
テレビでもプロのプレーは観られますよね?



ふっ…ちあきちゃん、まだわかってねぇな。
テレビは“プレーの結果”を見せるだけだけど、VODは“技術の過程”を映してくれるんだ!
確かに!
テレビ中継じゃ“ナイスアプローチ”で終わっちゃうけど、
VODなら“クラブを選ぶ瞬間”や“打つ直前のルーティン”まで観られますもんね!



なるほど~!
じゃあ、渋野プロの50°ウェッジでの転がしを研究してみようかな!



その意気だ!
プロのウェッジ使いを目で見て、頭で理解して、真似して打つ――
これが、VOD観戦の醍醐味ってやつだな
📲 \今すぐVODで女子プロのショートゲームを学ぼう!/
🏌️♀️ VOD観戦で学べるプロのウェッジ戦略 TOP3
| 🏆 プロゴルファー | 🎯 ショートゲームの特徴 | 🔍 VODで注目するポイント |
|---|---|---|
| 渋野日向子 | ピッチ&ランの達人 | クラブ選びの素早さ&低弾道転がしの打ち方 |
| 西郷真央 | 高精度スピンショット | バックスピン時のフェース開閉&インパクト音 |
| 小祝さくら | 安定感抜群のアプローチ | 打つ前の素振り回数とフェース角の調整 |
🔍 VOD観戦の3つの活用法
- 同じ状況でのクラブ選択を比較する
→ **「50ヤードアプローチ」**で各プロが使うクラブを分析。 - ショット後のリアクションをチェックする
→ プロは、スピン量や転がり具合を確認する仕草をよくする。 - 自分の練習前後にVODで復習する
→ 練習後に「プロはどう打ってたか?」をVODで確認して反省。



ウェッジ上達のカギ?
それは、“VODでプロのプレーを盗み観る”――これに尽きる!
俺だって、**渋野プロのウェッジテクを観て“目からウロコ”**だったんだからな!
🎯 ウェッジ選びの答えは、VODの中に!
ウェッジ選びに正解はねぇ。
でも、プロがなぜそのウェッジを選び、その打ち方を選択したのか?
その「答え」は、VOD観戦の中にあるんだ。
✅ この記事での学びポイント(おさらい)
- 渋野プロが4本→3本に変更した理由は、距離ギャップ調整・ロングゲーム強化・攻めの姿勢。
- アマチュアは、距離感練習には4本体制が効果的。
- VOD観戦なら、女子プロたちの**「クラブ選びの思考」や「アプローチの技術」**を何度でも研究できる。
📲 \さぁ、あなたもVODで“プロのウェッジ戦略”を体感しよう!/
- 「渋野日向子プロの転がしアプローチ」をスローでじっくり分析!
- 「西郷真央プロのスピンアプローチ」でスピンのコツを学習!
- 「古江彩佳プロのバンカー脱出術」をマネして苦手克服!
👀 VOD観戦でプロの技術を“観て盗む”!
そして次のラウンドで、「プロみたいなウェッジショット!」と同伴者に驚かれる日がきっと来るぜ。



ウェッジ選びの記事を読んで終わり?
…そんな消極姿勢じゃ、ショートゲームは上達しねぇ。
VODでプロの技術を観察して、“生きたウェッジ感覚”を手に入れろ!